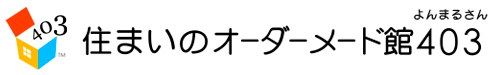源氏物語の頃の衣食住―4
源氏物語の色―紫の上の葡萄(えび)色と今様色

源氏物語は紫色の持つ「ゆかり(縁で結ばれている人、もの、こと)」が根底に流れていて、そのゆかりで深く繋がり描かれていくのが、桐壺更衣と藤壺女御と紫の上です。
以下の和歌が、この紫のゆかりの物語の源泉ともなったと言われる歌です。
「紫の一本ゆゑに武蔵野の草はみながらあはれとぞ見る」(たった一本の紫草があるゆえに、武蔵野に生えている草はすべていとおしく思われる)「古今和歌集」
源氏物語の中で、光源氏が数々の女性遍歴を重ねながら求め続けたのは、幼い頃に死別した生母の桐壺更衣とも、桐壺の面影を彷彿させた藤壺女御とも言われてきました。
しかし生母の桐壺更衣は、どんなに慕っても、既に亡き人で会うことは叶いません。
また藤壺女御は、一度は光源氏と過ちを犯しますが、我が子の出生の秘密を守り抜くため、母となった後は髪をおろして光源氏と距離を置き、逢うことを許しませんでした。
あの世の桐壺更衣は元より、現世でも恋しい藤壺に遭えなくなり、苦しい思いを抱いていたところに出会ったのが、藤壺によく似た姪にあたる幼女でした。
この可憐で愛らしい女の子は、幼い頃に光源氏に引き取られ、理想の女性として育てられ、妻となって紫の上と呼ばれます。
そして、紫の上は源氏物語に登場する数々の女人の中でも、最も光源氏に愛された女の主人公とも言われます。
しかし、大切に育てられたといっても、光源氏に引き取られたことも、理想の女性として育てられたことも、結婚したことも自らの意思ではありませんでした。
そして光源氏は紫の上と添いながらも、次々に他の女人とも関係を重ねていき、その一人の朧月夜との逢瀬が原因で、紫の上を残し、須磨に蟄居してしまいます。
その上、光源氏は紫の上との間には子をなさなかったのに、須磨にいる間に明石の君との間に子をなしてしまいます。
都に戻った光源氏は、その明石の君との子を都に引き取り、紫の上を育ての親とします。
明石の君の子ではありましたが、子ども好きな紫の上はこの子を大層慈しみ育て、しばし安寧の日が続きます。
しかし、紫の上は正式な妻ではなかったため、光源氏は女三宮を正式な妻として迎えてしまうことになります。
紫の上は改めて、自らが実に不安定な立場であると気づかされます。
その上、光源氏に引き取られ育てられた理由が藤壺女御に似ているからであり、女三宮も藤壺の姪で、互いに「紫のゆかり」同士であったことも知ることになってしまいます。
次々に知らされていく自らの身の上に気づいた時の紫の上の心情を思うと、あまりにも切なく哀れでなりません。
そんな紫の上の心の内に気づくこともなく、光源氏は六条院という広大な屋敷を建て、南西に秋好中宮、北東に花散里、北西に明石の上を住まわせ、自らは東南で紫の上と共に生活し、絶頂の時を過ごします。
玉鬘の帖では、光源氏は一緒に住む紫の上とともに、六条院の女人たちに布や衣装を選んでいきます。
当代一の他に並ぶことのない最高位にある光源氏から、紫の上は葡萄(えび)色と今様色を贈られます。
「紅梅のいと紋浮きたる葡萄(えび)染の御小袿、今様色のいとすぐれたる」(特別に紅梅の浮紋を施した葡萄色の打掛けと今様色の見事な衣)「玉鬘」
禁色に近い葡萄(えび)色は、高価で貴重な紫根を沢山使うとりわけ気品ある色で、今様色もまた高価な紅花染めによる紫みの強い赤色です。
光源氏が選んだ葡萄色とそれに合わせる今様色は、容姿も教養も人柄も、彼にとって理想の女人であった紫の上にふさわしい色でした。
しかし、光源氏は紫の上だけでなく、六条院の他の女人たちにも布を選んでいきます。
時には紫の上に相談しながら、それぞれに似合うらしい色を選ぶ光源氏の横にいなければならない紫の上の心情は、どのようなものだったでしょうか。
どの女人と関係を持っても、光源氏は紫の上の元に戻って来ては、やはり紫の上が一番だと言うのです。
光源氏に理想の女性として育てられた紫の上は、そんな光源氏の言動に対して、すねる風情は見せても、嫌なそぶりや言葉は出しません。
しかし実はその都度、紫の上の心には無数の傷が刻まれていき、次第に彼女の心は深く深く傷ついて、次第に紫の上の体と心は弱っていきます。
ついに長い間に心に住みついていった云い知れない懊悩からの解放を求め、紫の上は出家することを光源氏に願うのです。
しかし、紫の上を傍から離したくない光源氏は、紫の上の願いを聞き入れず、形ばかりの出家しか許しませんでした。
その後、最期の望みの出家も出来ないまま、紫の上は失意の中で亡くなってしまいます。
光源氏と一番長く過ごし、一番愛されたと言われる紫の上ですが、その生き方は自ら選んだものではなく、常に他の女人の影がちらつき、幸せと不幸せが繰り返されたものだったと思います。
あれほど女性遍歴を繰り返したにも関わらず、光源氏は最愛の紫の上を失ってしまうと、他の女人のところに通うこともなくなり、出家してのち、ほどなく亡くなります。
光源氏は一番大切だった人を失って、どれほど彼女に甘え、彼女を傷つけ、彼女を苦しめていたか、気づけたのでしょうか。
紫式部のゆかりの物語の主人公たちは、悲しいけれども人生のまことを伝えてくれているのかもしれません。
源氏物語の頃の食―平安時代の魚介類

平安時代の貴族たちの食卓には魚はよくのぼりました。
ただ京の都は海から遠かったので、新鮮な海産物を手に入れることは難しいことでした。
そのため、主に川や琵琶湖の魚介類、それも、腐らないように干物や塩漬けになったものが届けられました。
平安時代には、その保存方法が工夫され、種類も増えました。
例えば鮎なら煮乾年魚(塩水で煮てから火または日で乾かす)、塩漬年魚(内臓を除き塩を詰めて重石で押しをかける)、火干年魚(串に刺して火で乾かす)、鮨年魚(内臓を除き塩をして飯と交互に重ね押しをかける)、など、様々な方法で保存が出来るようになりました。
海藻は飛鳥時代から干物や塩蔵品にして税として納められていたようで、平安時代にもよく食べられていました。
平安中期の辞書ともいえる倭名類聚抄によると、ヒロメ、ニギメ、アラメ、ミル、アマノリなど20種以上の海藻が食用とされていました。
ところで、源氏物語の「常夏」の帖には、川の鮎や加茂川の石臥などを目の前で調理させて、という文章があります。
「親しき殿上人あまたさぶらひて、西川よりたてまつれる鮎、近き川のいしぶしやうのもの、御前にて調じて参らす。」(親しい殿上役人も数人集っていて、桂川の鮎、加茂川の石臥などというような魚を見る前で調理して差し上げる。)「常夏」
貴族でも、魚は干物や塩漬けしか食べられなかった当時に、光源氏は回りの近しい殿上人を集め、目の前で生の魚を調理して振舞いました。
この頃の光源氏が如何に栄耀栄華を極めていたかが分かるエピソードです。
源氏物語の頃の住まい―源氏物語の内裏

内裏とは、天皇の住まいで、儀式や執務などを行う宮殿のことです。
禁中・禁裏・御所などともいいます。
中央にあるのが、紫宸殿(ししんでん)で、宮中の行事を執り行う場所です。
源氏物語では第一帖の「桐壺」で、弘徽殿女御の第一皇子が御元服の儀式を行いました。
紫宸殿の北隣にあるのが天皇の私的な住まいの清涼殿で、清涼殿から北側の建物を後宮と呼び、帝に仕える女人たちが暮らしていました。
第七帖の「紅葉賀」では、この清涼殿の前庭で光源氏が頭の中将と共に舞楽「青海波」を舞いました。
後宮にはいくつもの殿がありました。
清涼殿の北隣が弘徽殿(こきでん)で、源氏物語では桐壺帝の第一皇子を産んだ弘徽殿女御の住まいでした。
光源氏の生母は、帝の寵愛を受けながらも更衣という低い身分だったため、最初は桐壺と呼ばれる北側で清涼殿から一番遠い淑景舎(しげいしゃ)にいました。
「桐壺」の帖には、桐壺更衣が清涼殿へ向かう度に弘徽殿女御をはじめ女房達のいじめに遭う様が描かれています。
それを知った桐壺帝により、桐壺更衣は遠い淑景舎から清涼殿の西隣の後涼殿へ移ることになりますが、源氏を産むと儚く亡くなってしまいます。
藤壺と呼ばれた後涼殿の北隣の飛香舎(ひぎょうしゃ)は、桐壺帝が桐壺更衣亡きあと、桐壺にそっくりな先帝の皇女を女御として迎えた御殿で、この藤壺女御を源氏は恋慕し、源氏物語が始まるのです。
風呂敷エコバッグ(スーパー編)
風呂敷があれば、エコバッグや紙袋の代わりになります。
一番簡単で沢山入る風呂敷エコバッグは、隣合う端と端を真結びするのを両側ですれば出来あがりです。
四角い箱、長いもの、丸いもの、瓶や不定形なものも、全て一緒に包んで運べます。
大判の100㎝前後四方の風呂敷なら、スーパーのかご一杯の買い物が持ち運べます。






1分で出来る「ふふふふろしき~風呂敷エコバッグ」