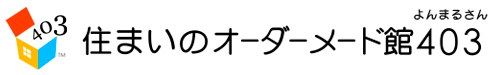源氏物語の頃の衣食住―3
源氏物語の色―桐壺の薄紫と藤壺の藤色

桐壺更衣は身分は高くはないけれど、帝の寵愛を一身に受けた女人でした。
しかし、光源氏を生むと3年もしないうちになくなってしまいます。
桐壺更衣の死に帝は大層悲しみました。
その後、桐壺更衣に瓜二つの皇女がいると聞き、妃に迎え入れたのが藤壺女御でした。
その頃、帝の側で育てられていた光源氏は、亡き母にそっくりで5歳しか違わない藤壺を姉のように慕い、姉弟のように過ごしました。
しかし元服後、藤壺と自由に会えなくなると、光源氏の藤壺への思慕の思いは激しい恋慕へと変わっていきます。
ついにある夜、光源氏は里帰りをしていた藤壺の元に忍び込み、藤壺は光源氏の子を宿してしまいます。
藤壺の懐妊を喜び、産まれた子を我が子と信じた帝は、藤壺を中宮とし、その子を東宮にたてます。
藤壺は名実ともに桐壺帝の一番の后となりますが、その心の中は帝を裏切った申し訳なさと、秘密が露呈しないかとの不安で、心が休まる日は無かったのではないでしょうか。
のちに桐壺帝が譲位をした後は、光源氏の兄にあたる朱雀帝が継ぎ、ほどなく桐壺院は崩御します。
桐壺院亡きあと、光源氏に皇子の後見を頼りにしたい藤壺女御でしたが、光源氏は藤壺に求愛するばかり。
決して、周囲から皇子の我が子の出自に疑念を持たれてはならない。
我が子のためには何でもしようと決意して、光源氏から遠ざかるため、ついに藤壺女御は出家します。
一度は光源氏と過ちを犯しましたが、自らの髪をおろしてまで我が子を守り抜いた藤壺は、母となって、深い愛と鋼の意志を持った強い女性になっていきます。
ところで、桐壺の名の由来の「桐の花」は優しい薄紫色で、桐壺更衣のか弱く儚いイメージにぴったりです。
藤壺の名の由来の「藤の花」は、淡い青みのある紫色で、藤色は藤の花の色から名付けられました。
平安時代、紫は高貴な色であり、「藤」は藤原氏の象徴であったことから、藤色は「色の中の色」として尊ばれました。
桐壺帝に愛され、その美しさ聡明さから「輝く日の宮」とも呼ばれた藤壺にふさわしい高貴な色ということでしょう。
ところで、桐壺の薄紫色も、藤壺の藤色も紫色ですが、源氏物語には紫色の持つ「ゆかり(縁で結ばれている人、もの、こと)」が根底に流れています。
そのゆかりで描かれている女人が、桐壺と藤壺と紫の上です。
作者の藤式部は、桐壺は桐の花で、藤壺には藤の花で紫を忍ばせ、紫の上はその名を紫の上と名付けることで、紫のゆかりの物語を語り紡いでいったのです。
源氏物語の頃の食―平安時代の芋豆野菜

源氏物語の頃は、貴族階級は主食に米が食べられましたが、庶民の主食は、主に麦・粟・稗などの雑穀で、足りなければ芋や豆などを代わりに食べました。
豆類には大豆、小豆、黒豆、ささげ、エンドウ豆など、芋類には自然薯やクワイなどがありました。
芥川龍之介の「今昔物語」に出てくる芋粥の芋は、江戸時代に伝来したサツマイモではなく、自然薯を米と一緒に粥にしたものだと思われます。
貴族は肉や魚も食べられましたが、庶民の副食はもっぱら野菜でした。
平安時代中期に書かれた辞書である「和名類聚抄」の中で記されている食物で、一番種類が多いのは野菜です。
瓜類、葱類、韮、らっきょう、芹、じゅんさい、青菜、蕪、高菜、からし菜、蕗、茄子、あぶらな、わらび、牛蒡、うど、いたどり、蓬、蓮、葛、たけのこ、山菜類、きのこ類、などたくさんの野菜の名前が記されています。
源氏物語の文章の中には、若菜、筍、野老(ところという芋類)、土筆、芹、蕨、などが出てきます。
数は多くないですが、それぞれに季節を感じさせてくれる野の菜たちが登場します。
「この春は誰にか見せむ亡き人のかたみにつめる峰の早蕨(さわらび)」(今年の春は、誰に見せましょう。亡き人の形見として摘んだ峰の早蕨よ)「早蕨」
源氏物語の頃の住まい―寝殿造の室礼(しつらい)

この頃の貴族の住まいは、寝殿や対の屋(たいのや)を渡殿(わたどの)と呼ばれる渡り廊下で繋ぐ寝殿造りでした。
この寝殿造りの屋外と屋内を仕切っているのは、遣戸(やりど)と呼ばれる引き戸や、妻戸(つまど)と呼ばれる両開きの扉、蔀(しとみ)と呼ばれる雨戸状のものでした。
寝殿の中心の部屋が主人の生活スペースの母屋(もや)で、その周りには一間ずつの庇(ひさし)が四方に設けられ、その外側に簀子が設けられていました。
二間の母屋の東西のどちらかには、土壁によって覆われた塗籠(ぬりごめ)が作られていました。
塗籠は先祖代々伝わる宝物などを収納し、神聖な空間と考えられていましたが、平安後期には物置として使われるようになりました。
基本的に室内には塗籠以外は間仕切りはなく、その時々で様々な障屏具(しょうへいぐ)を置いて仕切りました。
儀式などのように広い空間が必要な時には、それらの障屏具を取り払い、私的な空間が必要な場合は、御簾や几帳などを使って仕切りました。
障屏具には、障子、御簾(みす)、几帳(きちょう)、壁代(かべしろ)、屏風(びょうぶ)、などがありました。
障子は襖(ふすま)や衝立(ついたて)、屏風(びょうぶ)などの総称ですが、源氏物語では、ほとんど襖障子のことを指します。
襖障子は現在の襖に当たり、母屋と庇の間の隔てとして使われました。
御簾とは、細かく割った竹を編んだ障屏具で、母屋や庇の間、廂と簀子の柱間や妻戸口などに垂らしました。
几帳は台の上に二本の柱を立て、柱の上に長い横木を渡し、薄絹や帷子をかけたもので、移動可能でした。
壁代は、壁の代わりに長押(なげし)から御簾の内側に垂らす布製の帳(とばり)です。
屏風は木の枠に小さい襖を繋いだようなもので、立てて間仕切りや装飾として使いました。
様々な儀式や行事にも対応出来るよう、これらの障屏具などで間仕切りし、調度を整えたり飾り付けたりすることを室礼(しつらい)と呼びました。
風呂敷で包帯代わり
思わぬ怪我をした時に、手元に包帯がなくても、風呂敷があれば包帯の代わりとして使えます。
三角に折り、端が出ないように帯状に折ります。
怪我をした部分に折った風呂敷を当て、抑えながら残りを斜めに巻いていきます。
両端を真結びにして固定すれば、とりあえず怪我した部分を保護できます。
画像は、巻いた風呂敷の間に保冷剤を挟んで冷やしています。

1分で出来る「ふふふふろしき~リボン包み」