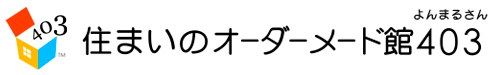和の暮らし
六月水無月
六月 水無月

六月の別名は「水無月」。
日本では六月は梅雨の時期で雨が多いのに、なぜ水が無い、というのだろう?そうお思いの方も多いかと思います。
水が無い、とは書きますが、実はこの「無」は、「の」に当たる連体詞で、「水無月」は、「水の月」ということだそう。
また、旧暦六月は、田んぼに水を張る時期でもあり、「水張り月」とよんだことが、変化して「みなづき」と呼ばれるようになったと いう説もあります。
昔は田んぼの仕事は村の農民みんなが協力しあってやったことから、「皆尽月」と名づけられ、 それが変化して「みなづき」となったという説もあります。
どの由来も、田んぼと水と関係していて、日本人の生活が稲作と共にあったことがわかります。
芒種(ぼうしゅ)

稲の穂先の針のような突起を禾(のぎ)と言います。
芒種とは、稲や麦など、この禾があり、その穂が出る植物の種を蒔く時期のことです。
この「芒種」の頃は、田植えの時期でもあり、田植え祭りも盛んに行われてきました。
みずほの国、日本ならではの節気です。
新暦では、6月5日頃から6月20日までです。
芒種の初候(新暦6月5日~9日頃)「蟷螂生ず(かまきりしょうず)」

カマキリが生まれ出る時期です。
カマキリのメスは、秋に葉や枝の裏に卵を産み付けます。
数百もの卵が一塊の泡状の卵鞘(らんしょう)に入って越冬し、この時期、一斉に孵化します。
自分より大きな相手でも威嚇するカマキリですが、実は田畑の害虫を食べてくれる益虫なのです。
芒種の次候(6月10日~15日頃)「腐草蛍となる(ふそうほたるとなる)」

蛍が幻想的な明かりをともし、飛び交う頃です。
蛍は別名を「朽草」とも言われます。
土の中で蛹だった蛍が、羽化して地上に現れる様子を見て、昔の人は朽ちた草が蛍に生まれ変わったと考えました。
「ほー、ほー、ほたる来い。こっちの水は甘いぞ。あっちの水は苦いぞ。」
子供の頃、こんな唱歌を歌いながら、蛍狩りをしたものですが、最近は、蛍が見られる清流も少なくなりました。
神秘的な蛍の光の情景がいつまでも見られるように、環境を守っていきたいですね。
芒種の末候(新暦6月16日~20日頃)「梅子黄なり(うめのみきなり)」

梅の実が熟して、黄色く色づく頃です。
梅酒用には熟す前の青い梅がよいですが、梅干しや梅酢用には、熟した梅が向いています。
梅は生では食べない方がよいですが、木から落ちるほどに完熟した梅は桃やすもものようで、砂糖と煮ると、美味しい梅ジャムになります。
梅雨の合間に、梅を使った梅仕事、いかがでしょう。
夏至(げし)

一年で一番日が長く、夜が短い頃です。
夏の真っ最中の気がしますが、日本では梅雨の時期と重なるので、暑さのピークはもう少し先です。
冬至にかぼちゃを食べるように、夏至にも食べ物の風習があります。
ただし、関西では蛸、京都では水無月という和菓子、福井では焼きサバ、関東では焼き餅というように、地方によってさまざまです。
新暦では6月21日頃から7月4日頃です。
夏至の初候(新暦6月21日~25日頃)「乃東枯る(なつかれくさかれる)」

「乃東」とはうつぼぐさの古名です。
うつぼぐさは夏枯草ともよばれ、古来より生薬として、洋の東西を問わず、役立ってきました。
花はきれいな紫色ですが、夏至の頃には花穂が黒ずんできて、枯れたように見えます。
それでこの時期を「乃東枯」と呼ぶようになりました。
夏至の次候(新暦6月26日~6月30日)「菖蒲華さく(あやめはなさく)」

菖蒲と書いて、あやめと読みます。
「いずれあやめかかきつばた」と言われるように、あやめもしょうぶもかきつばたもよく似ていますが、咲く時期や見た目である程度、見分けられます。
五月上旬から中旬に咲きはじめ、花弁の元のところに網目状の模様があるのが、あやめです。
梅雨到来を告げる目安の花でした。
夏至の末候(7月1日~4日頃)「半夏生ず(はんげしょうず)」

「半夏」とは、「烏柄杓」(からすびしゃく)の別名で、この植物が生える頃です。
農事には「半夏半作(はんげはんさく)」という言葉があり、夏至から半夏生の間に田植を終わらせることが大切とされてきました。
春から田植えまで働きづめだった体を労わる、農民の知恵なのかもしれません。
梅雨

六月の別名は「水無月」といいます。
六月は梅雨の時期で雨が多いのに、なぜ水が無い、というのでしょう。
水が無い、とは書きますが、実はこの「無」は、「の」に当たる連体詞で、「水無月」は、「水の月」ということです。
また、旧暦六月は、田んぼに水を張る時期でもあり、「水張り月」とよんだことが、変化して「みなづき」と呼ばれるようになったという説もあります。
梅雨は、この水無月を中心に、春から夏に季節が移り変わる際に、日本付近の前線が停滞し起こる現象です。
「梅雨」という言葉は、梅雨入りや梅雨明けなどの時には、「ツユ」と読み、梅雨前線の時のように、「バイウ」と読むこともあります。
この「梅雨」の語源もいくつかあります。
古代中国で、梅の実が熟す頃に降る雨ということから名付けられたという説。
又、黴が生えやすい時期の雨という意味で、「黴雨(バイウ)」と呼ばれるようになり、黴(カビ)では字の語感がよくなかったようで、同じ季節で読みも同じの「梅」の字を使い「梅雨(バイウ)」になったという説もあります。
日本に「梅雨(バイウ)」という言葉が伝わったのは、平安時代までさかのぼります。
この時代の詩歌集[藤原公任(ふじわらのきんとう)撰「和漢朗詠集」(わかんろうえいしゅう)]に「梅雨」という言葉を読んだ詩の一節があります。
実はこの時代は、梅雨のことを(さみだれ、さつきあめ)と呼ぶことが主流でした。
「さ」は五月、「みだれ」は「水垂れる」の意味です。
五月に雨とは少し早いのでは?と思われるかもしれませんが、この時代は旧暦を使っていて、現在の6月にあたります。
現在の歳時記で、同様な時期として使われるものがあります。
「五月晴れ(さつきばれ)」は、本来、梅雨で雨が多い中の晴れ間のこと。
また、「五月闇(さつきやみ)」は、梅雨の空の暗さを表す言葉として使われた言葉です。
バイウと呼ばれていた梅雨ですが、その後、江戸時代に、日本では(ツユ)に変わって行きました。
江戸時代の「日本歳時記」の中に、「これを梅雨(ツユ)となづく」という記述がみられます。
「梅雨(ツユ)」の言葉の由来には、また様々な説があります。
木の葉などに降りる「露(ツユ)」から連想したとする説。
梅の実が熟して潰れる時期だから「つぶれる」を意味する言葉から関連付けたとする説。
又、食べ物や衣類に黴が生えたり腐ったりなど、駄目になりやすい時期だから、潰える(ついえる)、やつれ衰える、疲れるを意味する言葉の潰ゆ(ついゆ)が(ツユ)に変化したとする説。
これらの説どれもが、この季節の自然や植物に関連したものです。
人々が四季の移ろいを実によく観察していたことから、日本の言葉の数々が生まれたことが分かりますね。
入梅と梅雨入り

「梅雨」は六月水無月を中心に、春から夏に季節が移り変わる際に、日本付近の前線が停滞し起こる現象です。
この「梅雨」の季節に入ることを「入梅」とか「梅雨入り」といいます。
中国で出来た二十四節気に加えて、より季節の変化を掴むために日本独自に作られた暦が雑節です。
「入梅」は「八十八夜」などと同じくこの雑節で、暦の上では6月11日頃とされています。
「入梅」は「梅雨入り」と同義語のように記されている記述もありますが、実際の「梅雨入り」は暦通りにはなりません。
南北に長い日本では、実際の「梅雨入り」は沖縄から北海道まで約1ヶ月前後のずれが生じます。
このため「入梅」は暦の場合でのみ使い、気象庁などが天気予報で使うのは「梅雨入り」の方を使います。
ところで何故、「入梅」にしても「梅雨」にしても「梅雨入り」にしても、「梅」という字を使うのでしょうか?
古代中国で、梅の実が熟す頃に降る雨なので「梅雨」と名付けられたからとか、黴が生えやすい時期の雨で「黴雨(ばいう)」と呼ばれるようになったが、字の語感がよくないので、同時期に盛りで読みが同じである「梅」の字を使い「梅雨(ばいう)」になったとか、諸説あります。
この「梅雨(ばいう)」は日本で「梅雨(つゆ)」と読むようにもなりました。
「梅雨(つゆ)」と読む由来には、雨が沢山降って木々に露がつくことから「露(つゆ)」になったという説や、熟して潰れる時期でもあることから「潰ゆ(つゆ)」が「梅雨(つゆ)」になったという説などがあります。
いずれも梅がキーワードとなっており、梅雨は梅の季節ともいえるのです。
梅は生食することはなく、梅干し、梅酒、梅シロップなどの食品に加工すると、身体によく保存がきく食品になります。
とりわけ梅干しは、平安時代には効用について書かれた書物がありました。
日持ちがよく、殺菌・整腸作用がある梅干しは、戦国時代には出陣前の縁起物や兵糧食として重宝されました。
江戸時代後半には「梅干しの七徳」といわれる効用が紹介されています。
「入梅」して雨が続く「梅雨」の間、同じ頃に盛りの梅を加工して、身体に効用のあるものを作り、鬱陶しい時期を乗り切って来た昔の人の知恵に感心します。
衣替え

「衣替(ころもが)え」は、季節の移り変わりに合わせ、衣服を替えることで、「衣更え」とも「更衣」とも書きます。
中国の風習だった衣替えは平安時代に伝わり、日本でも宮中行事として行われるようになりました。
時期としては旧暦の4月1日と10月1日に夏服と冬服を着替えるとし、更衣(こうい)と呼びました。
ただ天皇の着替えの役目を持つ女官も「更衣」という職名だったので、民間では「更衣」は「衣替え」に変わって行きました。
時代が下って行く間に、衣類だけでなく扇など身の回りの品にも広がり、鎌倉時代になると、調度品にも行われるようになりました。
江戸時代になると、幕府は出仕に際し、年4回の衣替えをするよう制度化し、庶民もそれに倣いました。
明治時代、政府は軍人や警察官の制服を洋服にし、夏服・冬服の衣替えの時期を制定しました。
1973年に新暦となり、6月1日から9月30日までが夏服、10月1日から翌年の5月31日までが冬服とされました。
そして官公庁や企業、学校などで6月1日と10月1日に衣替えを行うようになり、全国に広がっていきました。
現在は温暖化が進み、服装の自由度も増してきて、衣替えの風習も個人個人で変わってきています。
和服の世界では季節ごとの衣替えのしきたりが重要視されていました。
着物には袷(あわせ)、単衣(ひとえ)、薄物(うすもの)、表と裏の間に綿を入れる綿入れなどがあり、それぞれ着る時期が決められていました。
10月から5月末までは袷、6月と9月は単衣、7月8月は薄物、10月から3月は袷に綿を入れました。
一年のうち半分を綿入れを着ていたのは、江戸時代までは今と比べかなり気温が低く、冬が長く寒かったからです。
ただ時代が下って現代では、次第に温暖化や住宅事情が変わって来て、今では綿入れを着ることはなくなりました。
他にも和装の世界には素材や着方などに細かい決め事がありますが、ますますヒートアイランド化している今、しきたりに縛られることなく、肌で感じる季節に合わせ、心地よく自由に楽しむ方がよいと思います。
ただ古来からの和装のしきたりには、文様を使う季節の決まり事などもあり、季節を先取りし、四季の風物を感じさせてくれます。
季節を楽しめるしきたりは残しながら、心地よく過ごせる「衣替え」をしたいですね。
父の日

アメリカから伝わった「母の日」は、5月の第二日曜日と日本でも定着しています。
母の日に比べると多少影が薄いけれど、6月第三日曜日は、「父の日」です。
「父の日」は、ソノラ・スマート・ドットという女性が、「母の日」のように、父親にも感謝する日を作って欲しいと、牧師協会へ嘆願したことがきっかけで始まりました。
ソノラの母親は、父親が南北戦争で兵士として招集されると、女手ひとつで6人の子どもを抱え、働いて一家を支えました。
南北戦争が終わり、父親が復員するとまもなく、母親は亡くなってしまいます。
残された父親は、ソノラを末っ子に6人の子供たちを男手ひとつで育て上げました。
再婚することもなく、働きづめで子供たちを成人させた後、父親は亡くなりました。
そんな父の姿を見て育ったソノラに、母に感謝する日があるなら、父にも感謝する日を!という思いが生まれたのは、当然のことかもしれませんね。
ソノラが父親にも感謝する日を作って欲しいと牧師協会に嘆願したのは1909年で、翌年の6月19日には、父の日の祝典などが行われましたが、一般にはまだまだ知られていませんでした。
広く知られるようになったのは、1916年の父の日の祝典で、アメリカ合衆国第28代大統領ウッドロー・ウィルソンが演説をしたことがきっかけだったと言われています。
又、1966年には、アメリカ合衆国第36代大統領リンドン・ジョンソンが父の日を称賛する大統領告示を発し、6月の第3日曜日を父の日に定めました。
正式に「父の日」がアメリカの国の記念日とされたのは、1972年のことです。
日本で「父の日」が広まり始めたのは、1950年頃からで、まだ認知度は低く、より一般的に広まったのは1980年代になります。
その後、デパートなどで「父の日」の贈り物のイベントが行われたり、メディアでも取り上げるようになり、最近はお父さんに感謝する日として認知されるようになりました。
今年の「父の日」は、普段言えない感謝の言葉をお父さんに贈ってみてはいかがですか。
夏越の祓(なごしのはらえ)

六月の晦日日には、全国の神社で、夏越の祓(なごしのはらえ)という穢れを祓う行事が行われます。
今も昔も、人は日々の暮らしの中で、様々な間違いや過ちを犯すものです。
昔の人は、それらがだんだん穢れとなり身にまとわり重なり合って、病や災いをもたらすのを恐れました。
古くは一年を二つの時期に分けて考えていたので、半年毎の六月の晦日と十二月の晦日に、溜まった穢れを祓う大祓を行いました。
十二月の大晦日は年越しの時なので「年越の祓」と名付けられ、六月の晦日に行われるものは、「夏越の祓」と呼ばれました。
新暦の六月はまだ夏の初めですが、旧暦六月は、既に夏の夏の終わりの月でした。
六月晦日に行われる大祓えは、夏を過ぎ越える日の大祓えという意味で「夏越の祓」と呼ばれたのです。
又、夏越の祓は、六月水無月に行われるため、別名「水無月(みなづき)の祓」とも呼ばれました。
夏越の祓では、茅の輪(ちのわ)くぐりという行事をします。
茅の輪は、イネ科の多年生植物である茅(ちがや)で作った大きな輪です。
この茅の輪をくぐることで、病や禍を逃れることが出来ると考えました。
この行事は、「備後国風土記」の素戔嗚尊(すさのおのみこと)と蘇民将来(そみんしょうらい)の故事から生まれたものと言われています。
その昔、旅をしていた武塔(むとう)の神は、ある村で一夜の宿を求めました。
その村に、蘇民将来(そみんしょうらい)と巨旦将来(こたんしょうらい)という兄弟がいました。
巨旦将来は裕福であったにも関わらず、その依頼を断りましたが、蘇民将来は武塔の神を喜んで迎え入れ、もてなしました。
実はこの武塔は素戔嗚尊(スサノオノミコト)で、歓待してくれた蘇民将来へのお礼として、災厄を祓う茅の輪を授けました。
その茅の輪のおかげで、その後、村を襲った恐ろしい疫病から、蘇民将来とその家族だけは逃れることが出来たということです。
夏越の祓の茅の輪は、厄災や疫病を避けたいと願った人々の思いが込められた、疫病よけの霊力の象徴なのです。
茅の輪くぐりには、神社により多少違いますが、作法があります。
「千歳の命延ぶというなり(ちとせのいのちのぶというなり)」と古歌を唱えながら、最初は左からまわり、次は右へまわり、と、八の字を描くように、茅の輪を三度くぐります。
この、歩いて描く「八」の字、西洋では数学の∞(無限大)と同じ形です。
日本では古くから「八」が多く使われ、「古事記」や「日本書紀」にも「八」が沢山見られます。
三種の神器は、八咫鏡・八十握剣、八坂瓊勾玉と、全てに「八」という字がついています。
他にも、八咫烏、八十建,八衢、八重雲、と「八」はたくさんある、という意味の日本の大切な数といえます。
方位により悪事災難を取除く祈願は八方除けといいます。
夏越の祓で行う、茅の輪くぐりが「八」の字を描くのも、八方除けの祈りが込められているのかもしれません。
おうちで楽しむ水無月の風呂敷タペストリー

鬱陶しい梅雨の雨も、紫陽花の花や蛙には嬉しい空から恵み。降り続く雨の日もおうちの中を楽しくさせてくれる風呂敷です。