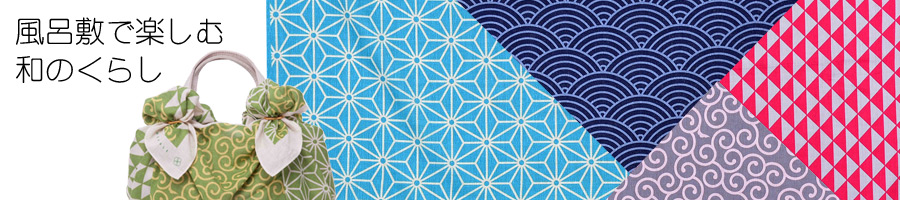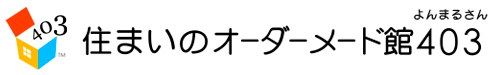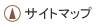日本の衣食住
皐月
端午の節句の鎧と兜

今では五月五日は端午の節句として子供の成長を祈るお祝いの行事となっていますが、古代中国では旧暦五月は、雨が多く天災や戦乱が重なり、禁忌多く忌み慎む月だったようです。
そのため、五月五日は無病息災を願い、邪気払いや魔除けの行事が色々行われました。
人々は野に出て草を踏み、持ち帰った蓬や菖蒲を門戸や軒下に吊るしたり、摘んだ薬草で薬湯に入ったり、薬草酒を飲んだりして邪気払いをしたそうです。
日本も旧暦の五月のこの時期は、梅雨で水の被害が出たり、ものも傷みやすく体調を崩しやすい時期だったので、中国のこれらの邪気払いが伝わると、自然に宮中行事として取り入れられていきました。
時代が下り、これらの行事が公家から武家に引き継がれるうち、端午の節句につきものの「菖蒲」は「尚武(武を尊ぶ)」と読めることから、武家社会では端午の節句を男子の節句として行うようになりました。
江戸時代になると、五月五日は五節供として式日となり、武家では男子が生まれると門前に家紋を記した幟を立て、鎧兜や弓矢などを飾り、男子の成長を寿ぎ祈りました。
戦の時代、鎧兜は武士にとって敵の攻撃から身を守るための大切な道具でした。
これらを飾るということは、病気や事故などから男児を守り、元気に丈夫に成長し、人生の困難に打ち勝っていって欲しいという親の願いが込められています。
端午の節供の粽(ちまき)と柏餅

端午の節句の和菓子といえば、粽と柏餅でしょう。
粽は、もち米や餅を笹や真菰の葉で円錐形や三角形に包み、い草で縛り、蒸したりゆでたりしたものです。
「ちまき」という名前が付いたのは、古くは茅(ちがや)の葉で包んだことに由来するそうです。
粽には、ある伝説が語り継がれています。
古代中国の楚の政治家で詩人であった屈原は、陰謀により国を追われ、国の将来に絶望し、汨羅(べきら)江に身を投げました。
屈原を慕っていた人々は、屈原の霊を慰めるため、命日の5月5日に米を入れた竹筒をマコモの葉で包み、五色の糸で縛ったものを流すようになりました。
これが粽の始まりと言い伝えられており、屈原の命日が5月5日であったことから、端午の節供に供されるようになったということです。
柏餅は上新粉で作った餅を平たい丸形にして、中に餡を挟んで二つに折り柏の葉に包んだ和菓子です。
柏の木の葉は、新芽が出るまで古い葉が落ちません。
昔の人はその新芽を子ども、古い葉を親に見立てて、親が子の成長を大事に見守ると考え、柏の葉は「家の存続」と「子孫繁栄」の象徴とされるようになりました。
その柏の葉で巻いた柏餅は縁起のいい食べ物として定着していき、徳川将軍家でも九代将軍家重から十代将軍家治の頃にこの縁起を取り入れました。
その後、端午の節句に柏餅を食べる風習は参勤交代で日本全国に行き渡りました。
柏餅の餡は粒餡、漉し餡、その他、味噌餡のものもあり、京都では白味噌餡を使うところもあります。
餅は基本的にはそのままの白い餅が多いですが、緑色の蓬生地の餅のものも作られています。
時代を経て、中国から伝わった粽は、伝統を重んじる京都をはじめ関西で伝承され、関東では柏餅が主流となりました。
又、日本の各地域で、べこ餅、笹巻、朴葉巻、あくまき、等々、その土地の特色を生かした和菓子が作られています。
どの和菓子も、子どもの健やかな成長を祈り生まれた産物なので、それぞれどれも引き継がれるとよいなと思います。
端午の節句の鯉のぼり

武家社会で男子の節供として行われるようになった端午の節句行事は、江戸時代、庶民の間にも広がっていきます。
しかし、幟旗を揚げることは、武家以外の庶民には許されませんでした。
代りに庶民は、中国の故事にある鯉が滝登りをして龍になるという「鯉の滝登り」にあやかり、武家の幟に似せて、鯉のぼりや吹き流しを立てるようになりました。
鯉のぼりが皐月の風に吹かれ、ゆうゆうと泳ぐ様に、人々は我が子の健やかな成長と立身出世を願ったのです。
又、鯉のぼりと共に揚げる吹流しの五色の色、青、白、赤、黒、黄、は、それぞれ仁・義・礼・智・信の五常の心を表しており、我が子を邪気や災いから守る、邪気祓いやお守りの意味があるとされています。
おうちで楽しむ皐月の風呂敷

端午の節句の鎧兜、今はなかなか全てを揃えて飾るのは難しいですが、風呂敷タペストリーなら可能です。
この風呂敷なら勇壮な鎧兜や弓矢、刀まで武具を一式楽しむことが出来ますよ。