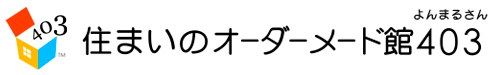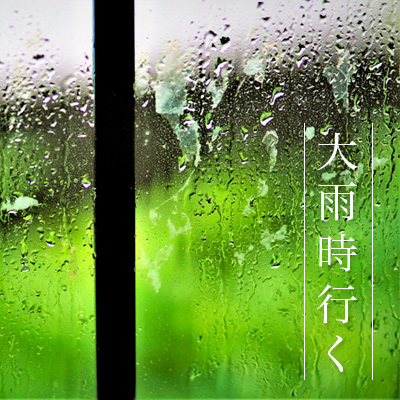和の暮らし
七月文月
七月 文月

七月の別名としては、文月、文披月、書披月、肇秋、など文や書に関わる別名、初秋、秋初月、秋染月、など秋に関わる別名、その他、七夕月、女郎花月、などがあります。
中でもやはり代表的なものは、文月でしょう。
文月の文は、書や手紙を意味しますが、これは七夕伝説の「乞巧奠(きこうでん」という風習に因んだものと思われます。
「乞巧奠」は、織姫彦星の星伝説と相まって、中国から伝わった行事です。
女性は織物や裁縫が上手くなるように、機織上手なこと座のベガ、織女星に願いをかけました。
彦星はわし座のアルタイルで、農事の開始の時期によく輝く星です。
この織女星と彦星の星伝説にちなみ、男女の願いをかけて行ったのが「乞巧奠」です。
本来は農耕のための天体観測でしたが、次第に貴族の時代の宮中行事になります。
貴族男子の仕事は、農耕ではなく、書類を書くことや詩歌を作ることでした。
それで、彦星に願うことは、書や文章の上達になっていきました。
「乞巧奠(きこうでん」は、まさに「文」の上達を祈る行事の月なので、「文月」という名がついたのだと思われます。
他には、稲穂が膨らむ月で、稲を含む「稲含み月」、それが、「含み月」となり、「ふみづき(文月)」となった、とも言われています。
こちらも米を食べて生きて来た瑞穂(みずほ)の国、日本だからこその「穂見月」で、「ふみづき」なのでしょう。
そして、初秋、秋初月、秋染月など、秋と名付けられた月名もあります。
実は旧暦では7月8月9月が秋で、7月は秋の始めの月なので、初秋なわけです。
月の名前には新暦でなく旧暦の季節感が込められているのです。
小暑(しょうしょ)

雨が続く梅雨が明けたら、暑い夏の到来です。
「小暑」とは、暑さが小さいと書きます。
まさに夏の幕開けの時期を表していますが、梅雨明け前、集中豪雨などに見舞われることもある頃です。
この「小暑」から「立秋」までが、暑中見舞いを送る時期です。
本来、暑中見舞いは、なかなか訪問して挨拶をすることが難しい、遠方の方への挨拶状でした。
それが大正の頃より、広く夏のご挨拶として送られるようになりました。
年々歳々暑くなる日本の夏、暑中見舞いで互いに元気に乗り切るエールを送りませんか?
新暦では、7月7日頃から7月21日頃までです。
小暑の初候(新暦7月7日~11日頃)「温風至る(あつかぜいたる)」

熱気をはらんだ風が吹いてくる頃です。
関東地方では内陸部の埼玉県熊谷市や群馬県館林市などが、よく最高気温を観測します。
東京などのヒートアイランドの熱が、これら内陸部の盆地に海風が運んでくるからだとも言われています。
まさに「温風至る」、ここから夏本番です。
小暑の次候(7月12日~16日頃)「蓮始めて開く(はすはじめてひらく)」

蓮の花が咲き始める頃です。
「蓮は泥より出でて泥の染まらず」とあるように、蓮は泥の中から出でて、清らで美しい花をさかせ、わずか4日で散ってしまいます。
黒い泥の中から見事に美しい大きな花を咲かせ、あっという間に散るその姿に、古代の人は俗世にまみれぬ気高さを見出し、極楽浄土を感じたのでしょう。
小暑の末候(新暦7月17日~21日頃)「鷹乃学を習う(たかわざをならう)」

鷹の雛が飛び方を覚え、獲物を捕らえる技を学び、巣立つ頃です。
古代、鷹狩りは「君主の猟」といわれ、皇族、貴族の特権でした。
又、日本古来の神事・儀式のための獲物を捕るにも欠かせない存在で、鷹を使って狩りをする鷹匠は、戦後まで宮内庁に所属していました。
歳時記に鷹が飛ぶことがあるのは、そういう理由からなのです。
大暑(たいしょ)

大暑とは厳しい暑さのことで、文字からして暑いことが分かりますね。
真夏の酷暑のことで、一年で一番暑い時期です。
暑さが厳しいこの時期、農家の方の農作業はさぞかし大変だと思いますが、そのおかげで、夏が旬のおいしい実りを沢山いただくことが出来ます。
この時期、旬の作物は、きゅうり、なす、いんげん、おくら、とうもろこし、ゴーヤ、すいか、と枚挙にいとまがありません。
魚もいわし、かます、すずき、かんぱち、あおりいか、するめいか、など美味しくなります。
ひまわりや朝顔、オシロイバナや芙蓉など酷暑にも負けず咲いてくれる健気な花たちは、大暑のひと時の安らぎです。
新暦では、7月22日頃から8月6日頃までです。
大暑の初候(新暦7月22日~27日頃)「桐始めて花を結ぶ(きりはじめてはなをむすぶ)」

桐の花が咲く頃です。
桐は日本で使われる材木としては最軽量で、湿気を通さない高級な木材です。
桐箪笥に代表されるように、桐は日本人のくらしの中で、家具として大いに役立ってきました。
その昔、日本では、女の子が生まれたら桐を植え、結婚する時には、その桐で箪笥を作り、嫁入り箪笥にしたものでした。
大暑の次候(新暦7月28日~8月1日)「土潤いて溽し暑し(つちうるおいてむしあつし)」

「土潤いて」は、土の中の水分を暑さが蒸発させることです。
「溽し暑し」は湿度が高く、蒸し蒸しと暑いことを言います。
足元からも湿気が上がり、じっとりまとわりつくように暑い時期です。
大暑の末候(8月2日~6日頃)「大雨時行く(たいうときどきふる)」
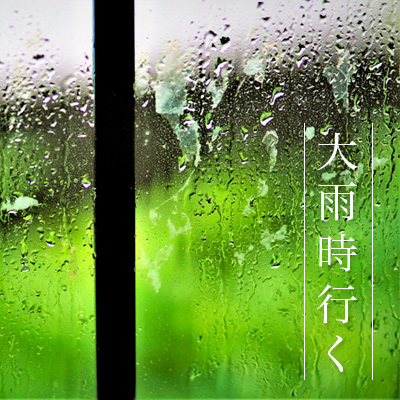
夏真っ盛り、一転にわかにかき曇り、豪雨や夕立が降ることを言います。
晴天で強い日差しが照り付けていたのに、夕方、急に入道雲がわき、突然ざぁーっと雨が降ることを夕立といいます。
夕立は降っても数十分で止むので、天然の打ち水でもありました。
七夕と三つの風習

今も続く、笹の葉に願いを書いた短冊を結び祈る七夕の行事は、実は江戸時代に生まれたものです。
七夕は中国から伝わった伝統的な風習や伝説と、日本で行われてきた行事などが重なり合って、今の形になったものと思われます。
諸説ありますが、大きくは三つのことが重なったとされています。
その一つが、「乞巧奠(きこうでん、きっこうでん)」。
中国から農耕や天文学を利用した暦が伝わって来た際に一緒に伝わったとされる風習です。
「乞巧奠」は、糸や針の仕事を司るといわれた「織女星(織姫星)」が輝いてよく見える「七夕」の夜、 中国で技巧や芸能の上達を願って行われた風習です。
これが、日本の宮中にも広まり、宮中の女性達が、機織やお裁縫が上手くなる事を祈り、御供え物をする女性の祭りとなったと言われています。
二つ目は、中国で農耕のための天体観測から生まれた「星伝説」です。
七夕といえば天の川ですが、七月七日によく見えるでしょうか?
実は現在の七夕、7月7日は、大抵は梅雨の時期で、天候が悪いことが多く、星を見るには適していません。
昔は旧暦で行われていたので、七夕は現在の八月でした。
この頃は星の群れの天の川を挟んで、こと座のベガの「織姫星」、わし座のアルタイルの「彦星」が、よく見えます。
中国では古くから「彦星」は農耕に適した時期に明るく見えるので、「農事」の基準とする星と考えました。
同様に天の川を挟み輝く「織姫星」を養蚕や織物、針仕事の星と考えるようになったようです。
この星伝説が日本に伝わり、農業が本格的になる時期と、星が良く見える夜に「七夕」を行う様になったのです。
三つ目は、日本に古くから伝わる棚機女(たなばたつめ)信仰です。
棚機女とは、水辺で神の衣を織りながら神の訪れを待ち、やがて神の妻となる巫女となる乙女のことで、機で織った布を棚にかけていくことから、棚機女と名付けられました。
七夕の行事は、中国から伝わった「乞巧奠」と「星伝説」が混ざり合い、「七夕」行事になってきたと考えられます。
行事の内容には残りませんでしたが、「棚機女」の「棚機」は、「七夕」がたなばたと読む由来として現在も残っています。
日本のモノコトを調べる度、毎回感じることがあります。
日本人は外からの異質な文化を、良いと思えば排除せず、良い部分だけ実に上手に日本文化と融合させてきました。
排除すれば衝突し争いになる。
全部容れれば占領される。
そこを争わず、実に見事に取捨選択しながら融合させてきた結果を、この「七夕」に見ることが出来るように思います。
今は単に笹の葉に短冊を飾る行事となった「七夕」ですが、実に豊かで賢い日本の選択の結実として、改めて見直したいものです。
土用と丑の日

土用は中国の陰陽五行説から来た言葉で、本来は「土旺用事」で、それが略され、土用となりました。
「土旺用事」は、「土の気が旺(さかん)になり事を用うる」という意味で、又「旺」は、働きという意味があり、土の気が最もよく働く期間を示します。
陰陽五行説は、自然界のあらゆるものを「蔭」と「陽」にわけた「陰陽論」と、自然界は木(もく)火(か)土(ど)金(ごん)水(すい)の5つの要素で成り立つとする「五行説」を組み合わせ、あらゆる現象を説明する理論です。
その五行説の5つの要素を四季にあてはめると「土」だけが残ります。
そこで、各季節の変わり目の18日間を「土」を割り当て、それを「土用」としました。
ですので、本来は土用は春夏秋冬四回あったのですが、現在は夏土用のみを土用というようになりました。
夏の土用は暑い盛りで夏バテしがちです。
それで、土用餅、土用卵、土用しじみなど、夏土用には精がつく食べ物をとるようになりました。
ところで土用といえば「土用の鰻」を思い起こすかと思います。
鰻は万葉集の巻十六に、大伴家持が吉田石麻呂の夏痩せを見て『石麻呂にわれもの申す夏痩せに良しというものぞ鰻捕り食せ』と歌った歌があります。
このようにかなり古くから、体力が落ちる夏には、鰻を食べて精をつける風習があったことがわかります。
それでは土用なら何時でもよいはずが、なぜ丑の日が特別に言われるようになったのでしょう?
これには諸説ありますが、代表的なものは平賀源内説です。
元々、夏の土用の丑の日には「うのつく食べ物を食べると夏負けしない」という言い伝えがあり、うどんや梅干しなどが食べられていました。
鰻も「う」がつくけれど、実は鰻は冬眠を前に身に栄養分を蓄える、晩秋から初冬が最も美味しい時期で、夏はあまり食べられていませんでした。
そのため、ある鰻屋が夏場に鰻が売れないで困り、源内先生に相談をもちかけました。
すると源内先生、「本日、土用の丑の日」という大きな看板(又は幟)を出し、鰻を食べると薬になると宣伝しなさい。」とアドバイスしたそう。
その結果、その鰻屋さんは大層繁盛し、その後は他の鰻屋さんも真似るようになり、「土用の丑の日には鰻を食べる」風習が定着した、ということ。
他にも諸説ありますが、味が落ちる夏の鰻を売る為の商人の知恵が、実はこの優れたキャッチフレーズの生みの親かもしれないなと思ったりもします。
ともかくも、ビタミンAやDが豊富な鰻、丑の日だけでなく是非夏は頂きましょう。
日本人と鰻

日本人が鰻を食べ始めたのは、かなり古くからで、先史時代より食べられていたようです。
鰻がはじめて記録に書かれたのは8世紀の「風土記」で、「万葉集」にも詠われています。
調理法は、14世紀の「鈴鹿家記」に出てきますが今の調理法とは全く違うものでした。
その調理法は、鰻をぶつ切りにし、串に刺して焼くもので、その形が蒲の穂ににているから、蒲焼という名前になったと言われています。
味付けは、醤油や味噌、塩、酢などでしたが、醤油は鰻から出る脂で弾かれてしみ込まず、あまり好まれませんでした。
のちに、今のように鰻を裂いて骨を取り、串を打って焼くようになりましたが、まだ味付けはまだ味噌や酢が主流でした。
その後、千葉の野田や、銚子などで作られる関東の濃口しょうゆが普及するにつれ、しょうゆ味の蒲焼が生まれてきます。
鰻のたれは、鰻屋さんでそれぞれ味付けが違いますが、基本はしょうゆとみりんです。
山椒や酒などを加えることもありましたが、次第に現在のしょうゆとみりんを合わせた甘辛いたれの味に近くなったようです。
江戸の町でも、関東風と関西風が混じって売られていたようですが、19世紀以降は関東風の味付けになりました。
この甘辛い蒲焼になると、ご飯のおかずにふさわしくなります。
それまで、蒲焼だけしか売られていなかった鰻屋や蒲焼屋に加え、「めしや」としての鰻屋が登場し、「うな丼」が生まれます。
19世紀半ばに出版された「守貞漫稿」には、「うなぎめし」の説明が書かれています。
鰻は美味しいだけでなく、目によいビタミンA、疲労回復のビタミンB1、美容効果のあるB2、骨や歯を強くするビタミンDやカルシウム、老化防止のビタミンE、免疫力を高める亜鉛、さらに脂質の部分にはDHA、EPAも豊富に含まれています。
うなぎの体の表面のぬるぬるした部分にはムチンという胃腸の粘膜を保護する成分が含まれていて、どこを取っても「栄養」の「最高の健康食」なのです。
日本人は栄養たっぷりの鰻を頂いて、体力をつけて夏の暑い時期を元気に乗り越えようとしてきたのですね。
お中元

日頃の感謝の気持ちを込めて、お世話になっている人に贈る夏の贈答がお中元です。
しかし、お中元の語源の「中元」は元々は贈り物をするという意味合いではありませんでした。
この「中元」という言葉は、古代中国で生まれた道教の思想に基づくものです。
道教では一年を上元、中元、下元の三つに区切って考えます。
旧暦で一年を三分し、旧暦1月15日を上元、7月15日を中元、10月15日を下元とし、これらの日に神に供物を捧げる行事が行われていました。
偶然にもこの道教の中元の日は、仏教ではご先祖様を供養する盂蘭盆会(うらぼんえ)という行事を行う日でした。
道教の中元と仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)は、時間が経つにつれ混同され、いつの間にかひとつの行事になって行きました。
そしてこの行事が日本に伝わり、ご先祖様を供養するお盆の行事になっていきます。
更に江戸時代になると、お盆にご先祖様へ供養のお供えをするとともに、お世話になって方々へ贈り物をおくる習慣にも変化していきました。
明治時代には、「お中元には、お世話になった人に贈答品を贈りましょう」というコマーシャルも登場しました。
いつのまにか、「お中元」といえば夏の贈答、あるいは贈答品を指すようになったのです。
暑中見舞い

手軽にメッセージを送ることが出来るメールが生まれる以前は、連絡する手段は手紙か電話でした。
遠方だと電話代がかさむので、手紙やハガキをよく書いたものでした。
お正月の年賀状に次いで、まとめて沢山やりとりがあったのは「暑中見舞い」でした。
年賀状と同様、普段なかなか会えない方やお世話になった方、遠方の知人友人などとやり取りが出来、暑い夏に互いの健康を気遣うことや、近況を知ることが出来るよい機会でした。
この風習の元が生まれたのは江戸時代頃と言われています。
お盆に里帰りする際にご先祖様へ供養のお供えを持ち帰ることが、親やお世話になった方々への贈答の習慣に変わって行き、持参出来ない遠方のお宅へは飛脚便で贈り物を贈るようになりました。
その後、次第に贈答の習慣は簡素化され、品物は挨拶状に変わって行き、「暑中見舞い」という形になりました。
「暑中見舞い」を贈る時期は、七月中旬から立秋まで、立秋以降は「残暑見舞い」とされています。
「暑中見舞い」は猛暑に体を壊されませんように、「残暑見舞い」は夏の疲れが出ませんように、どちらも先様の暑い季節の健康と無事を気遣う便りでした。
近年、手軽なメールという機能が出来たため、新年のご挨拶の年賀状も辞める方が増えてきました。
ましてや暑中見舞いのやりとりは、もっと少なくなってきたようです。
しかし、暑い盛りに頂く「暑中見舞い」には、目から涼やかにと金魚や西瓜の挿絵があったり、こちらへの気遣いの言葉が記されりと、夏の疲れが癒される爽やかさと思いやりを頂けます。
皆様も今年は親戚の方や知人友人の方に「暑中見舞い」を書いて、夏の優しい癒しを届けませんか?
おうちで楽しむ文月の風呂敷タペストリー「七夕飾り」柄の風呂敷

深い藍色の七夕の夜空に、点描で描かれたような細かい星が夜空にびっしりちりばめられ、笹の枝に飾られた笹飾りも天の川へ飛んでいる風呂敷です。